矯正治療
ちゃんと信頼できるところで歯の矯正をしたい。
そんなあなたに、紹介したい専門医がいます。
ちゃんと信頼できるところで
歯の矯正をしたい。
そんなあなたに、
紹介したい専門医がいます。
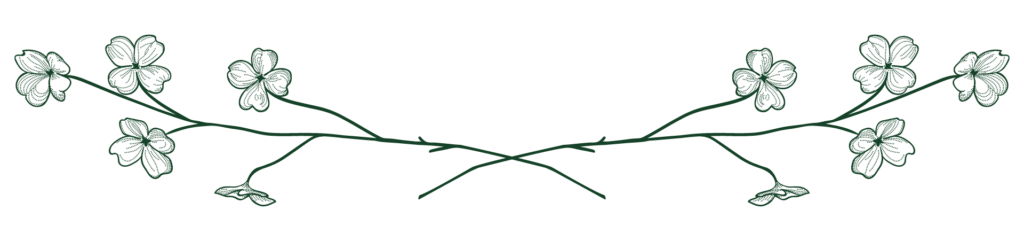
この先生でよかった。
すべては、その一言のために。

歯の矯正について、このような悩みを抱えていませんか?
「抜歯が必要と言われたけど、できれば抜きたくない」
「マウスピース矯正で本当に治るのか不安」
治療方針が違う」
「抜歯が必要と言われたけど、
できれば抜きたくない」
「マウスピース矯正で
本当に治るのか不安」
臨床指導医(旧称:専門医)が在籍する安心感
臨床指導医(旧称:専門医)が
在籍する安心感
患者さんにとっては、どの歯科医院を選ぶかが治療の質を左右する非常に重要なポイントだと思います。当院では、日本矯正歯科学会認定の「臨床指導医(旧称:専門医)」資格を有する矯正歯科医が診療を担当しております。この「臨床指導医(旧称:専門医)」という資格は、単なる肩書きではなく、長年にわたる臨床経験、症例の多様性、そして高い倫理観と教育的な役割が認められた証です。
がもっとも大切
とは何か?

信頼できる専門家とともに
「自分に合った治療法は?」「費用はどのくらい?」といった疑問も丁寧にお答えします。「どこで治療するか」ではなく、「誰に診てもらうか」。その判断材料として、「臨床指導医(旧称:専門医)の存在」を、ぜひ覚えておいていただけたら幸いです。

- 1998年 東北大学歯学部卒業
- 2002年 東北大学大学院歯学研究科博士課程修了(歯学博士)
- 2003年 日本矯正歯科学会認定医取得
-
2021年 日本矯正歯科学会臨床指導医(旧称:専門医)取得
詳しくはこちら>>
- 1998年 東北大学歯学部卒業
- 2002年 東北大学大学院歯学研究科博士課程修了(歯学博士)
- 2003年 日本矯正歯科学会認定医取得
-
2021年 日本矯正歯科学会臨床指導医(旧称:専門医)取得
詳しくはこちら>>
- 2002~2003年 東北大学歯学部附属病院医員
- 2003~2006年 東北大学大学院歯学研究科助手
- 2006〜2009年 一般歯科・矯正歯科開業医勤務
- 2009~2024年 仙台青葉クリニック(旧歯科一番町)勤務
- 2002~2003年 東北大学歯学部附属病院医員
- 2003~2006年 東北大学大学院歯学研究科助手
- 2006〜2009年 一般歯科・矯正歯科開業医勤務
- 2009~2024年 仙台青葉クリニック(旧歯科一番町)勤務
- 日本矯正歯科学会
- 東北矯正歯科学会
- 日本舌側矯正歯科学会
- 日本矯正歯科学会
- 東北矯正歯科学会
- 日本舌側矯正歯科学会
- 2004年 口腔の成育をはかる 2巻(医歯薬出版:分担著書)
- 2007年 OrthoTADs -The Clinical Guide and Atlas-(Under dog media:分担著書)
- 2020年 「デイモンブラケットとアンカープレートを適用した骨格性反対咬合」臨床家のための矯正YEAR BOOK 2020(クインテッセンス出版:分担著書)
- 2021年 「アライナーを用いた埋伏歯の予防:症例報告」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume1 isse1(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2022年 「アライナーを用いた埋伏歯の牽引」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume2 isse1(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2022年 「TADとアライナー型矯正装置:成人矯正治療における審美的な期待に応えるためのコンビネーション」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume2 isse3(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2022年 「口腔再建リハビリテーションにおけるアライナー矯正治療」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume2 isse4(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2004年 口腔の成育をはかる 2巻(医歯薬出版:分担著書)
- 2007年 OrthoTADs -The Clinical Guide and Atlas-(Under dog media:分担著書)
- 2020年 「デイモンブラケットとアンカープレートを適用した骨格性反対咬合」臨床家のための矯正YEAR BOOK 2020(クインテッセンス出版:分担著書)
- 2021年 「アライナーを用いた埋伏歯の予防:症例報告」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume1 isse1(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2022年 「アライナーを用いた埋伏歯の牽引」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume2 isse1(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2022年 「TADとアライナー型矯正装置:成人矯正治療における審美的な期待に応えるためのコンビネーション」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume2 isse3(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2022年 「口腔再建リハビリテーションにおけるアライナー矯正治療」JOURNAL OF ALIGNER ORTHODONTICS日本語版 volume2 isse4(クインテッセンス出版:分担翻訳)
- 2013年 「下顎大臼歯の遠心移動前後における根尖部および周囲組織のCBCTを用いた定性的評価」東北矯正歯科学会学術大会
- 2016年「当院における非外科的矯正患者への最近のTADs適用状況について」第1回日本歯科矯正用アンカースクリュー研究会(優秀発表賞)
- 2017年 「What are the Indications of Orthodontics Miniplates?」WIOC
- 2018年 「矯正歯科医から見たSendai Surgery First法の特徴」Surgery First Summitプレシンポジウム
- 2022年 「成長期の矯正歯科治療を考える:RTDモデレーター」第81回日本矯正歯科学会学術大会
- 2022年 「TADsを効果的に適用するための治療戦略」第38回東北矯正歯科学会秋季セミナー
- 2013年 「下顎大臼歯の遠心移動前後における根尖部および周囲組織のCBCTを用いた定性的評価」東北矯正歯科学会学術大会
- 2016年「当院における非外科的矯正患者への最近のTADs適用状況について」第1回日本歯科矯正用アンカースクリュー研究会(優秀発表賞)
- 2017年 「What are the Indications of Orthodontics Miniplates?」WIOC
- 2018年 「矯正歯科医から見たSendai Surgery First法の特徴」Surgery First Summitプレシンポジウム
- 2022年 「成長期の矯正歯科治療を考える:RTDモデレーター」第81回日本矯正歯科学会学術大会
- 2022年 「TADsを効果的に適用するための治療戦略」第38回東北矯正歯科学会秋季セミナー
- オームコセミナー講師、プロシードセミナー講師、WHITE CROSSセミナー動画配信など
- オームコセミナー講師、プロシードセミナー講師、WHITE CROSSセミナー動画配信など
大人の矯正治療の流れ


相談
まずは丁寧にお話をお聞きします。
どのようなお悩みがあるのか、何をどこまで治したいのか、
ご遠慮なくお聞かせください。プロとしての考え方をベースに、
可能な限りご要望を優先いたします。そして、
口腔内写真をお見せしながら、予想される治療プランの概略や
料金の概算について説明いたします。
まずは丁寧にお話をお聞きします。どのようなお悩みがあるのか、何をどこまで治したいのか、ご遠慮なくお聞かせください。プロとしての考え方をベースに、可能な限りご要望を優先いたします。そして、口腔内写真をお見せしながら、予想される治療プランの概略や料金の概算について説明いたします。
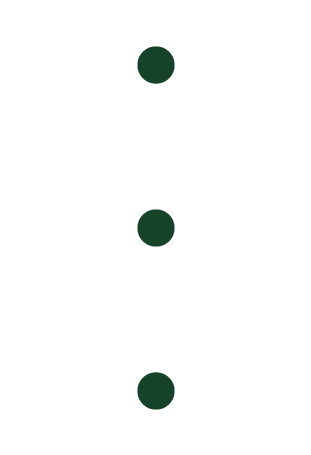
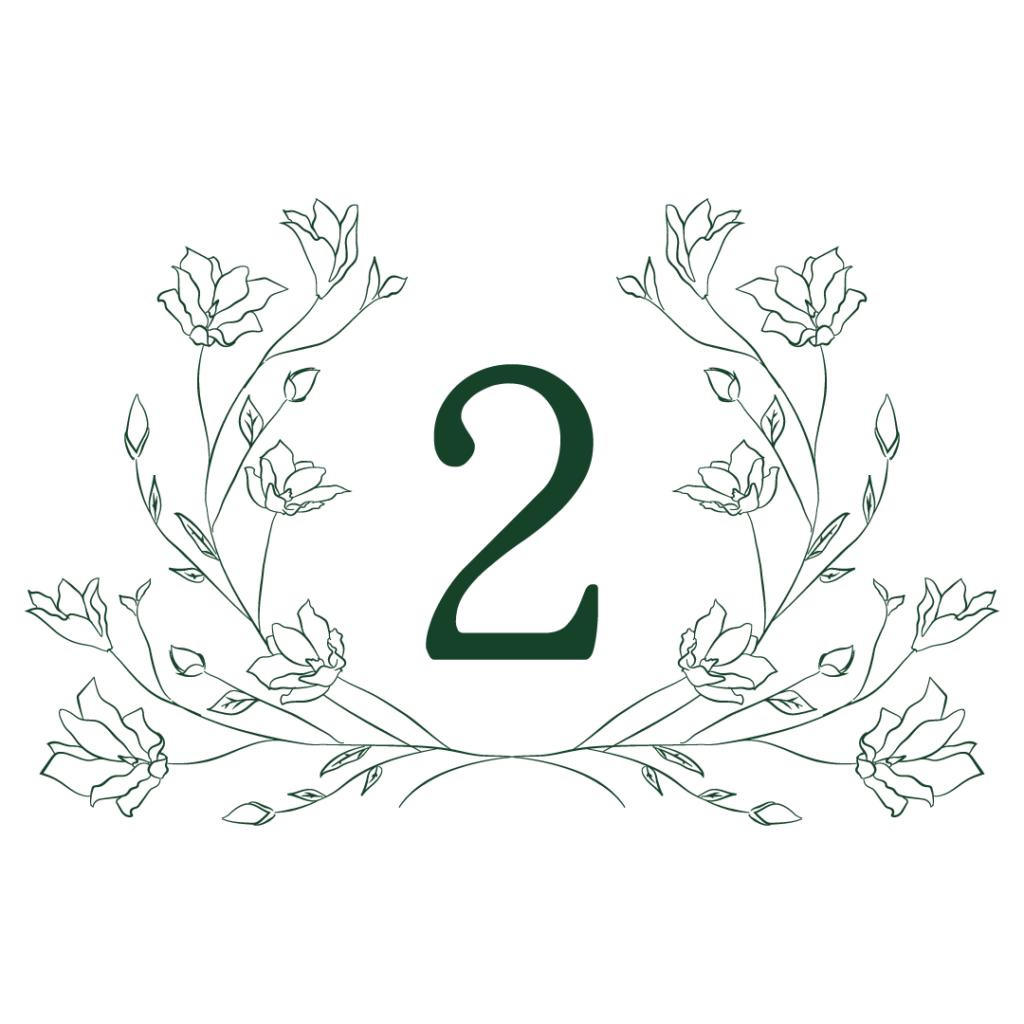
精密検査
矯正治療には精密な検査が必要です。
診査、各種レントゲン写真撮影、顔と口腔内の写真撮影、
歯型または口腔内スキャナーを用いた光学スキャン、などを行います。
なお、当院のレントゲンは患者さんの被ばく線量や
身体的負担の軽減に優れた最新機器を使用しています。
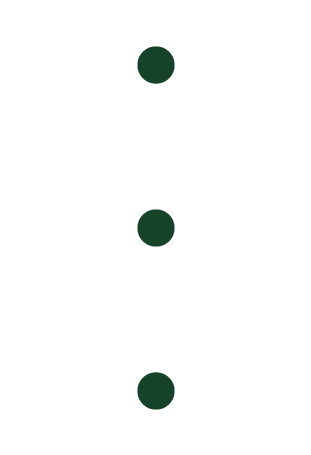
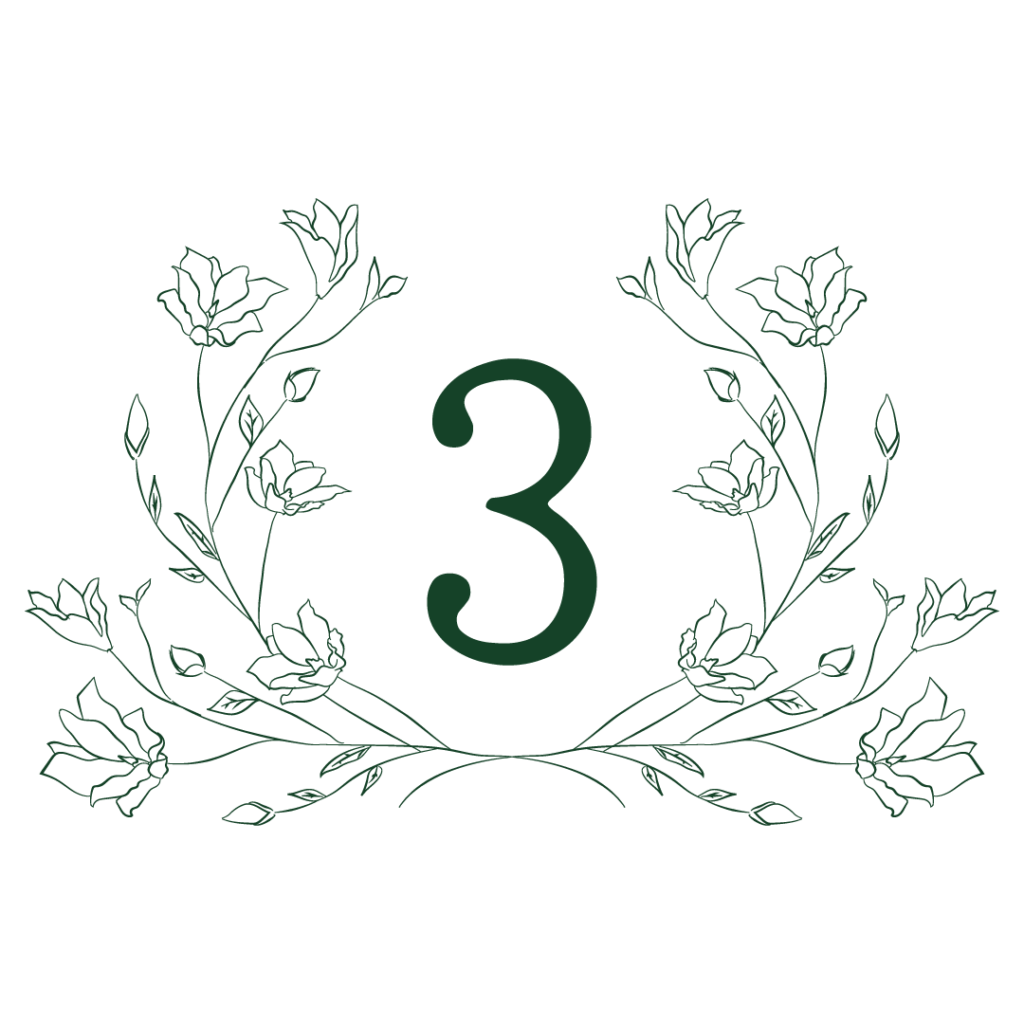
診断
検査結果から、現在どのような問題があるのか、
そして、どのような治療が必要で、治療期間の見込みは
どのくらいなのか説明いたします。また、
複数の治療の選択肢がある場合は、
それぞれのメリット・デメリットを比較し、
治療方針の選択を行います。なお、治療内容は個人個人で
全て異なりますので、それに応じた治療費を事前に提示いたします。
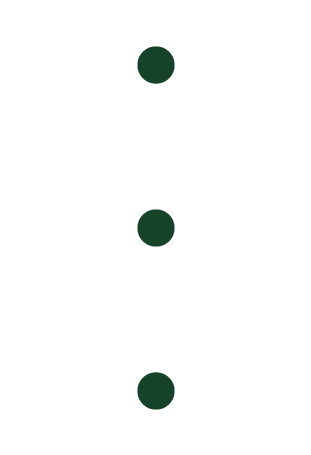

口腔衛生指導
矯正治療で歯並び咬み合わせが綺麗になっても、
虫歯や歯周病で健康を損ねてしまうのは
本末転倒だと私たちは考えています。
そのため、矯正装置を使い始める前に、
適切な歯みがき指導や食事の指導を行うことで、
予防処置を大切にしております。
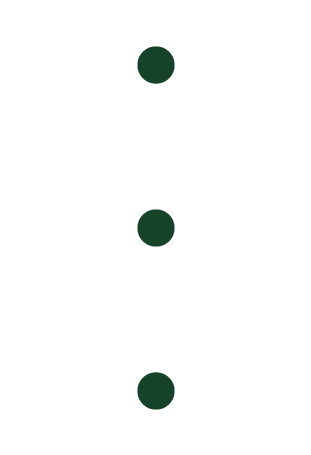

矯正治療
各種矯正装置を用いて治療を開始します。
通常、3〜4週間ごとの通院となります。
治療期間は症状によって幅があり、
1〜3年が目安となります。
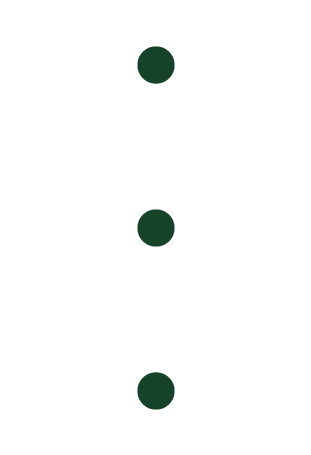

保定観察・メンテナンス
歯を動かす治療が終了した後は、
綺麗になった歯並びを安定させる保定というステージになります。
通常は年に1〜2回来院いただいて、
装置の確認や歯並び咬み合わせのチェックを行います。
保定期間は2年を目標としていますが、
その後は患者さんの状態やご要望により、調整していきます。
こどもの矯正治療の流れ


相談
ご本人だけでなく、ご家族のお話を伺って診察していきます。
現在だけでなく将来予測される問題を考えることで、
すぐに治療が必要なのか、必要なら
どのような治療となるのかを説明いたします。
あごの成長や歯の生えかわりのある、こどもの矯正治療では、
今気になっている目の前のことだけでなく、
その後の人生を考え、長期に渡る変化を俯瞰的視野から
考えることが大切です。
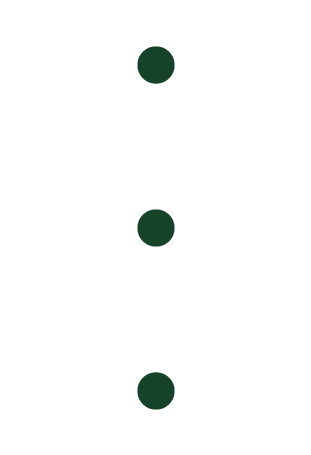
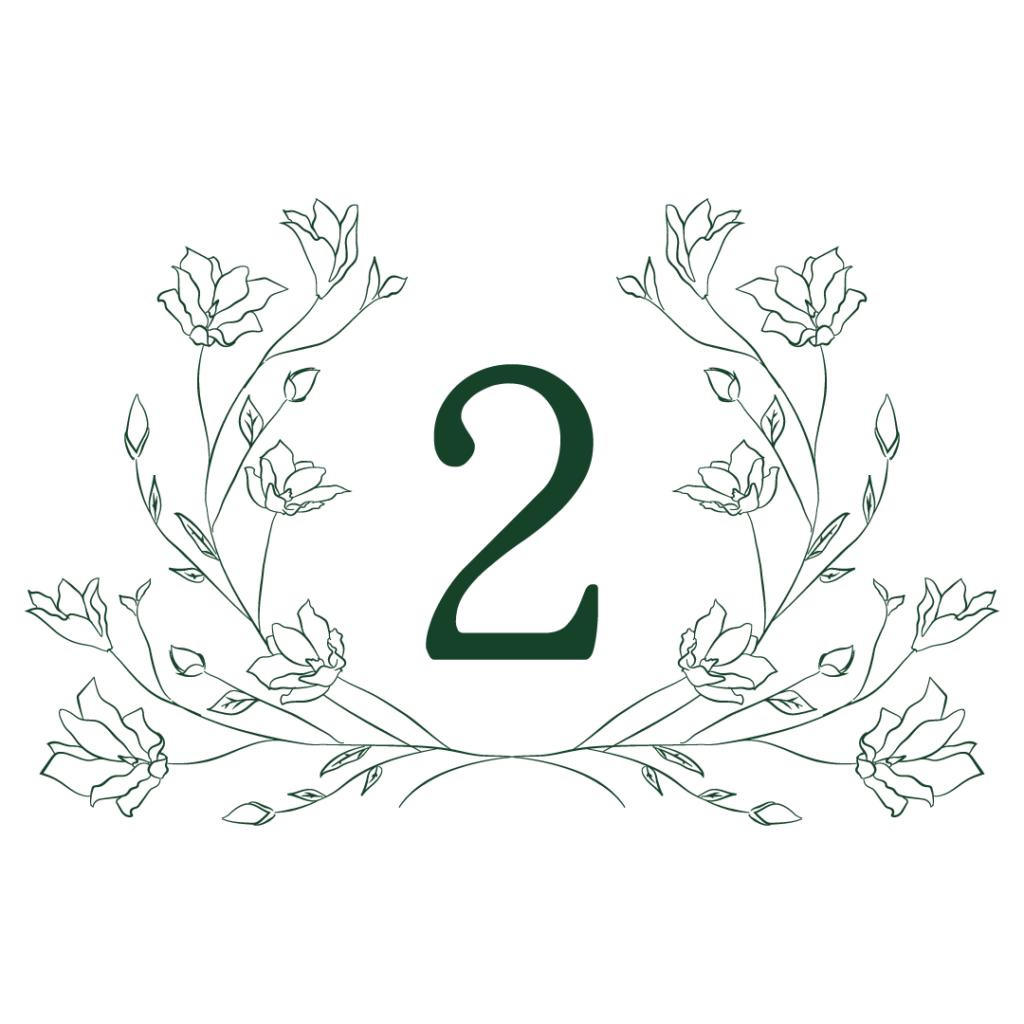
精密検査
矯正治療には精密な検査が必要です。
診査、各種レントゲン写真撮影、顔と口腔内の写真撮影、
歯型または口腔内スキャナーを用いた光学スキャン、などを行います。
なお、当院のレントゲンは患者さんの被ばく線量や
身体的負担の軽減に優れた最新機器を使用しています。
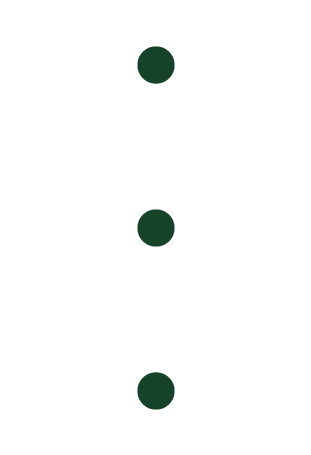
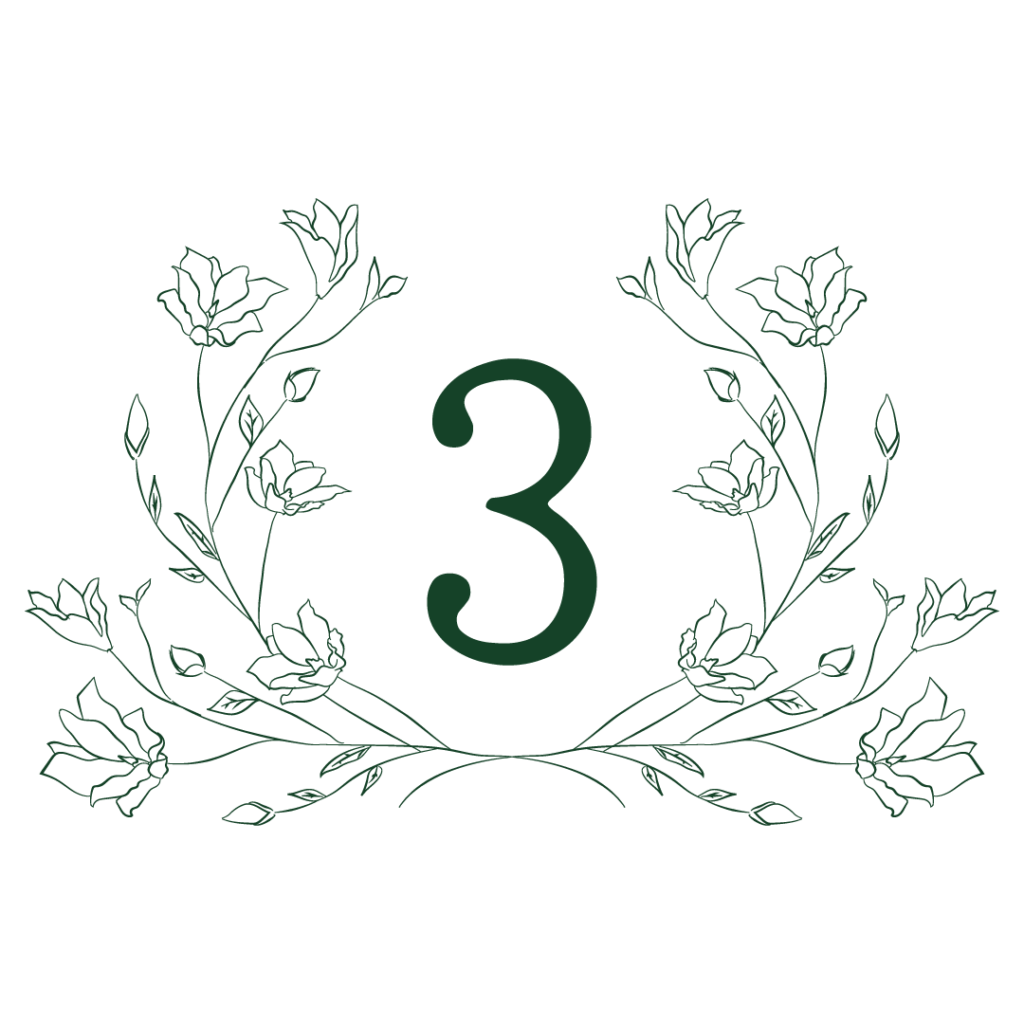
診断
検査結果から、現在どのような問題があるのか、
そして、どのような治療が必要で、
治療期間の見込みはどのくらいなのか説明いたします。
また、第1期の治療が必要かどうかなど、
複数の治療選択肢がある場合は、
それぞれのメリット・デメリットを比較して、
治療方針の選択を行います。
なお、治療内容は個人個人で全て異なりますので、
事前にそれに応じた治療費を明確にご提示いたします。
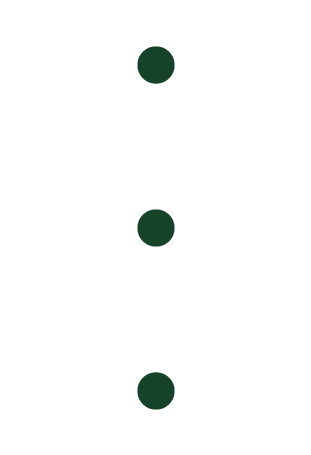

口腔衛生指導
お子様の生涯にわたる健康づくりのため、
こどもの時期からの予防処置を大切にしております。
そのため、矯正装置を使い始める前に、
適切な歯みがき指導や食事の指導を行います。
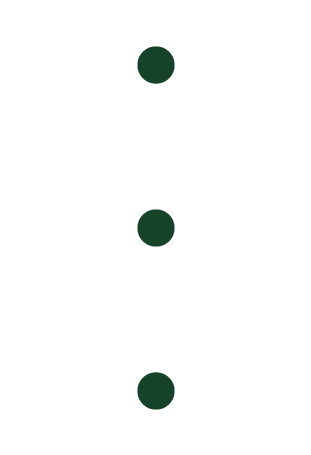

第1期矯正治療
第1期治療では、乳歯がある時期、
年齢では6才から12才頃までを対象の目安とします。
主にあごの成長や歯の生えかわりを利用した治療を行います。
とりわけ見過ごせない問題があれば重点的に治療します。
通常、3〜4週間ごとの通院となります。
期間は1〜2年を目安として、
なるべく短期間で終わるように目標を設定します。
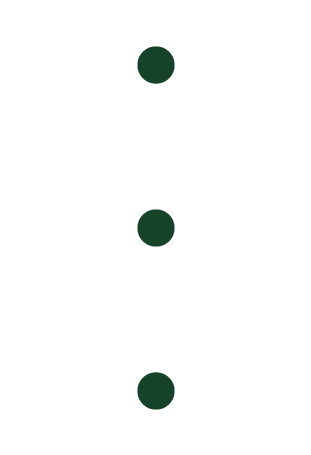

成長観察
第1期治療終了後、成長と保定の観察を行います。
この時期は、虫歯や歯肉炎の予防を重視して、口腔衛生ケアを継続いたします。
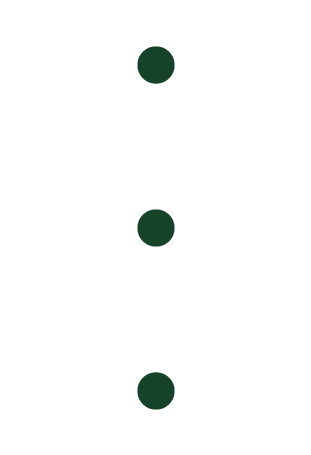

第2期矯正治療
永久歯が生え揃い、あごの成長がほぼ終了した段階を見極めて、
第2期矯正治療が必要かどうかを検討します。
ご本人の意思を大切にして、治療の必要性があるかどうか、
あればどのような内容になるのかをアドバイスします。
この、仕上げとなる第2期矯正治療では、
全ての永久歯をコントロールします。
治療内容は大人の矯正治療に準拠します。
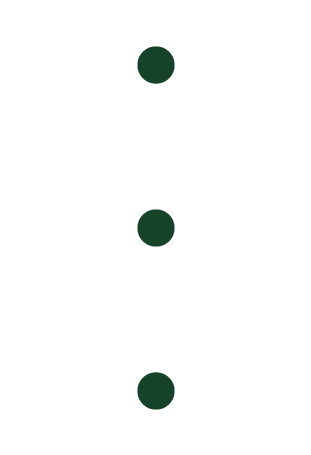

保定観察・メンテナンス
歯を動かす治療が終了した後は、
綺麗になった歯並びを安定させる保定というステージになります。
通常は年に1〜2回来院いただいて、
装置の確認や歯並び咬み合わせのチェックを行います。
保定期間は2年を目標としていますが、
その後は患者さんの状態やご要望により、調整していきます。
矯正歯科治療に伴う
一般的なリスクや副作用について

- ① 最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間~1、2 週間で慣れることが多いです。
- ② 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。
- ③ 装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正治療には患者さんの協力が不可欠であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
- ④ 治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりすることが重要です。また、歯が動いた結果、隠れていたむし歯が見つかることがあります。
- ⑤ 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきがやせて下がることがあります。
- ⑥ ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
- ⑦ ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
- ⑧ 治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
- ⑨ 治療中に「顎関節から音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
- ⑩ 様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。
- ⑪ 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。
- ⑫ 矯正装置を誤飲する可能性があります。
- ⑬ 装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
- ⑭ 装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
- ⑮ 装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。
- ⑯ あごの成長発育によりかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。
- ⑰ 治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になることがあります。
- ⑱ 矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。
診療内容

汎用性が高いため、効率性や予測性の高い治療を目指せる
表側装置を許容する必要がある
装置が目立ちにくい、装置の違和感が少ない、自分で取り外しができる
(食事やブラッシングが楽になる)
使用時間が不足したり使用方法が不完全だと計画通りに治療が進まない
(ご自身のライフスタイルに合うかどうかが重要となります)
装置が目立ちにくい、取り外しの手間が必要ない
舌の違和感や発音に影響することがある、他の治療法より治療期間や治療費がかかる
骨格から根本的な改善が期待できる
大学病院と連携した全身麻酔による外科手術が必要となる
用いた矯正治療
歯の移動効率を向上させることで、治療期間の短縮に有効である
矯正治療に伴う非抜歯率がある程度向上する
局所麻酔下による処置が必要となる
アンカースクリューに対する衛生ケアが必要となる
用いた矯正治療
矯正治療に伴う抜歯を避ける治療選択肢が増える
歯の移動効率を向上させることで、治療期間の短縮に有効である
外科矯正の回避がある程度可能となる
医療連携による、局所麻酔下による小手術が必要となる
アンカープレートに対する衛生ケアと炎症の予防が特に重要となる
を用いた第0.5期的治療
なお、その後には次のステップとして第1期治療を行うかどうかの検討が必要となります。こどもの時期からの矯正治療には定期的な診察が大変重要で長期に渡ることから、ご本人のご負担と治療効果を見極めながら総合的に判断することが何より大切です。
山田先生からの
メッセージ

「抜歯が必要と言われたけど、できれば抜きたくない」
「マウスピース矯正で本当に治るのか不安」
